AIで資格をマッチング
回答
サービス介助士試験について
 この記事は、文字実が執筆しました。
この記事は、文字実が執筆しました。
サービス介助士試験とは、生活扶助などに関する能力を有するかどうかを試すための資格試験で、民間資格とされています。
ホームヘルパー講習で多くの時間を占める「入浴・排泄・食事」の学習を省き、自宅学習と実技教習で学べるのがサービス介助士です。
高齢者・障害者が積極的に街中に出かけられる環境づくりを担うホスピタリティマインドのある人材を育成することを目的として設置された福祉の資格です。
サービス介助士試験は、2級と3級が設置されています。
サービス介助士試験の概要
受験資格
受験制限は特にありません。誰でも受験することができます。
試験内容
通信教育課程、自宅でのインターネットを使ったストリーミング学習、実技教習課程、検定試験を経て、合格者にサービス介助士が認定されます。
試験科目
〜通信課程〜
6カ月間の自宅学習で課題を提出します。60点以上で合格、60点未満の場合は再提出しなければなりません。
1、サービス介助の基本理念
2、高齢者社会の理解
3、高齢の方への理解
4、障害のある方への理解
5、バリアーフリーサービスの基礎知識
6、ホスピタリティーマインドと接遇技術
7、具体的介助技術
8、地域社会への貢献
9、超高齢社会を迎えての法規等の凡例
〜実技実習〜 6時間×2日間
1、オリエンテーション
2、ディスカッション「高齢者ってどんな人」
3、高齢者擬似体験
4、ディスカッション「体験の感想」など
5、ジェロントロジー(創齢学)とは
6、ホスピタリティーマインド・接遇訓練
7、車椅子操作方法・演習・移乗訓練
8、聴覚障害の方への介助
9、歩行に支障がある方への介助
10、視覚障害の方への介助・演習
11、ユニバーサルデザイン・共用品
12、車椅子操作と手引きの実技チェック
13、総合ロールプレイ ほか
〜検定試験〜
筆記試験、50問
申込み期間
希望する開講月の前日の15日まで。
試験日
各地域によって開講日が異なります。以下を参考にしてください。
毎月4回開講:東京
2〜3ヵ月に1回開講:仙台、名古屋、大阪、香川、福岡、沖縄
受験料
39,900円(税込)
講座の教材、提出課題の添削、実技教習、検定試験、認定証発行料などの費用を含みます。
その他
〜サービス介助士取得の流れ〜
2級取得の流れ
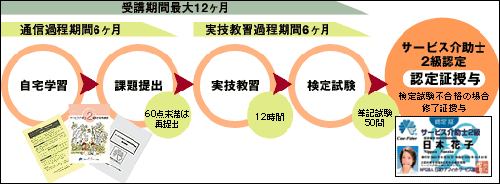
3級取得の流れ
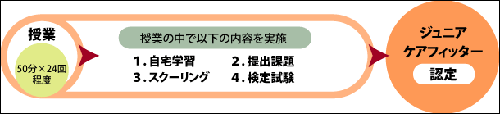
サービス介助士試験についてのコメント
サービス介助士試験について詳しい人や何か知っている人からのコメント(体験談等)を募集しています。
サービス介助士試験に興味がある人に役立ちますので、知っていることがあれば何でも大丈夫ですので、ぜひコメントをお願い致します。
![]() 0件
0件


